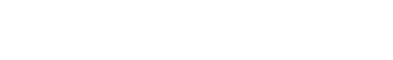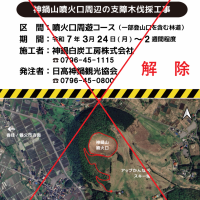神鍋神社の由来と創建の歩み
________________________________________
神鍋神社について
神鍋神社は、1999年に神鍋火山の噴火口付近に建立された神社であり、その由来は地域の文化と自然環境を尊重する人々の想いに深く根ざし、「火山」「自然」「山」の神々を祀り地域の象徴として愛され、訪れるすべての人々に安らぎと感動を与える場所であり続けることが祈願され、創建されました。
今日では、神鍋高原の美しい景観と豊かな自然を守り続けるシンボルとして、地域住民と訪れる人々を繋ぐ存在として人々に親しまれています。
現在、神鍋神社の御朱印を頒布しておりますので、こちらも併せてご覧下さい。
________________________________________
創建の背景
神鍋高原は、火山をシンボルとした高原地帯であり、古くから火山に感謝と畏敬の念を込めた「火山祭り」が行われてきました。
しかし、火山祭りを行うにあたり「神社が無いのは適切ではない」という声が上がり、神社を建立する動きが始まりました。
この計画を推進したのは、当時の観光協会長(飯田正治郎氏)を中心とした有志でした。
「火山をシンボルとするこの高原にふさわしい神社を建てることで、自然環境と地域文化を未来に伝えたい」。 その強い想いが神鍋神社創建の原動力となりました。
________________________________________
次世代への想いと地域のシンボル、御神体と祀られる神々
神鍋神社には、火山、自然、山を象徴する神々が祀られています。これらの神々は、以下の3つの神社から御神体を分けていただき、神鍋高原の守護神としてお迎えしました。
1.火の神 京都 愛宕神社(あたごじんじゃ)
主祭神:伊奘冉尊(いざなみのみこと)
由 来:日本神話において、伊奘冉尊は国産み・神産みを司る女神であり、火の神である火之迦具土神を生んだ際に命を落としたとされています。火に関わる神として、火山と火の力を象徴しています。
神鍋神社での意義:近畿で唯一、噴火口が残る火山を中心として7箇所の火山で成り立つ高原だからこそ火山を敬う地域の願いから、火山に関わる神として伊奘冉尊を祀りました。
2.景観美の神 奈良 大神神社(おおみわじんじゃ)
主祭神:大物主大神(おおものぬしのおおかみ)
由 来:大物主大神は、大国主命(おおくにぬしのみこと)の別名ともされ、国造り、農業、酒造り、縁結びの神として信仰されています。また、大神神社は三輪山を御神体としており、自然崇拝の象徴となっています。
神鍋神社での意義:神鍋高原の美しい自然環境を守りたいという地域の願いから、自然を守る神として大物主大神を祀りました。これは、景観そのものではなく、自然そのものを保護し、恵みをもたらす神としての信仰に基づいています。
3.山の神 愛媛 大山祇神社(おおやまづみじんじゃ)
主祭神:愛媛 大山祇神(おおやまづみのかみ)
由 来:大山祇神は、山の神々の総元締めとされ、山林や海の守護神として広く信仰されています。古来より山は神聖な場所とされ、自然の恵みと共に人々の生活を支えてきました。
神鍋神社での意義:「山を大切にしたい」という地域の想いを形にするため、山の神である大山祇神を祀ることで、神鍋高原の山々への感謝と敬意を表しています。
________________________________________
建設の特徴
神鍋神社の設計には、以下のような特徴があります。
1.形状の由来:ケルンをモチーフにした設計
登山者が山頂に積み上げるケルンをモチーフにしており、「日本で一番大きなケルンを作りたい」という目標が掲げられました。
使用された素材
火山の恵みを象徴する設計として、社自体に使用される岩石は地域の火山岩を使用し、一部(扉・内壁・看板)以外は全て地域の岩石が使用されています。
(平成6年の但馬の祭典に伴い作られたゆとろぎ温泉の建設時に出た溶岩を使用)
2.地元素材の活用と耐久性への配慮
次世代への負担を減らしたいという地域住民の願いもあり、「草が生えても腐らない社」を目指して設計され、耐久性の高い素材(岩石)を選ぶことで、長期的な維持管理が容易になるよう工夫すると共に、神様をしっかりとお迎えしたいという厳粛な思いが込められています。
3.看板の書
日高町十戸地区にある戸神社(とのじんじゃ)の吉田神主自らが筆を取り、看板に文字を刻みました。地元の歴史と伝統を象徴するものとして、大切にされています。